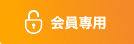通関士試験 合格体験記
第57回通関士試験に合格された皆様、おめでとうございます。
今年度、当連合会の通関士試験突破研修を受講者から55名以上の通関士試験合格者が誕生しました。
お忙しい中どのように勉強時間を確保したか、勉強方法やモチベーションの維持方法など、今後「通関士試験」合格を目指す方にぜひとも参考にしていただきたい体験記です。
株式会社サンオーシャン 野村 茉莉 様
エムオーエアロジスティックス株式会社 小泉 陽和 様

丸全昭和運輸(株) 中山 大輔 様
北海運輸株式会社 井上 裕輔 様

株式会社近鉄トレーディングサービス 須江 祐人 様
私は貿易実務業務に携わっており、通関業務に直接は携わってはいませんが、自分自身の知識の幅を広げるために、通関士試験の受験を決めました。
今回が初めての受験でしたが、通関連合会のテキストや講義動画、模擬試験のおかげで計画的に勉強することができ、合格することができ本当に良かったです。
関税法、通関業法、通関実務の3科目のうち、一番難易度が高いのは通関実務であるということは噂に聞いていたので、通関実務の勉強をなるべく早く始めることができるように、関税法や通関業法の勉強を4月と5月の2ヶ月間で詰め込みました。完全に定着させることはできませんでしたが、通関実務は「習うより慣れろ」で数をこなした方がいいため、6月と7月でどんどんテキストの問題に取り組みました。ある程度の基礎知識さえあれば解ける問題も多く、演習を重ねるうちに次第に正答率も上がってきました。通関連合会から送られるテキストや模擬試験で演習を重ねることができたことが、合格できた大きな要因だったと思います。
関税法や関税定率法は、テキストを見るだけではどこがポイントなのかがわからず、覚えることも膨大なため、テキストを読む前に講義動画を見ることにしていました。また、講義動画は月毎に定期的にアップされ、youtubeで見れるようになっていたため、毎日の通勤時間や昼休憩を活用しながら計画的に勉強することができました。
関税法、通関業法、通関実務の3科目の勉強がある程度終わった後は、徹底的に過去問に取り組みました。通関連合会のテキストや模擬試験に加えて、市販の過去問題集を購入し、10年分ほど解きました。最初は特に通関実務の科目で、最初からつまずいてしまい全然得点が取れないということもあったり、難しい問題に頭を悩ませて時間が足りなくなってしまうということがありましたが、10年分を解き終わった時には、6割前後の得点を安定して取れるようになっていました。
最後になりますが、通関士の試験勉強を応援してくれた会社や講師の方々に感謝を申し上げるとともに、これからは試験勉強を通じて学んだことを活かして業務に取り組んでいきたいと思います。
日通NECロジスティクス株式会社 和田 正志 様
私は通関士という資格があることは認識していたものの、特段必要とは考えていませんでした。ただ、業務上海外出荷に携わる中、通関の知識を取得しておいた方が良いと考え受験を決意しました。受験を決意したのち、一度の受験で合格することを目標に学習計画を立てました。ただ、市販の参考書での学習のみだと補えない部分があると感じたため、当講座を受講した次第です。
当講座を受講して良かった点は「スクーリング」、「模擬試験」、「当講座にて頂いた問題集」です。まず、スクーリングは市販の参考書で学習して理解しづらかった箇所を中心に視聴し苦手分野を作らないよう心掛けていました。また、スキマ時間である待ち時間などがあればできるだけスクーリングを視聴するようにし、モチベーションを下げないよう工夫していました。模擬試験は実際にアウトプットすることで自分の現状を定量的に把握する場として活用していました。どのあたりの点数が不足していて合格点に到達しないのかを分析し、こちらもスクーリングの視聴で改善していきました。また、6月という早い段階で模擬試験が届き、試験時間に合わせて問題を解くことになるので、自然と科目毎の試験時間感覚も身に付いたと感じています。最初の模擬試験では間違いが多く焦りましたが、直前に受けた模擬試験では合格点に達しており、本試験直前の自信に繋がりました。問題集については問題数が多く問題に慣れることができること、そして問題の傾向が掴めたことが非常に良かったです。また、計算問題も豊富にあるので、計算問題を解くスピードも上がったと実感しています。
私は勉強するときに集中して勉強し、集中力が途切れた時は小休憩するといったことを繰り返しながら勉強していました。いま、考えると少し休憩することでリフレッシュでき、より効果的に学習を進めることができたのかなと感じています。通関士試験は点を取れる問題と取りにくい問題があり、点を取れる問題を確実に取ることで合格に近づきます。勉強を継続し、点を取れる問題を増やしていくことが重要なのかなと思いました。
最後に、この度合格できたのは日本通関業連合会の皆様、また社内の方々等ご支援いただいた多くの方々のお陰と思っております。この場をお借りして感謝申し上げます。これから受験される皆様の合格を心よりお祈りしております。
株式会社上組 沖野 朱峰 様
通関士という資格を知ったのは、就職活動中に物流業界について調べているときでした。貿易関連で唯一の国家資格だと知り、当時武器になるような資格などを持っていなかったため、通関士資格取得を目指すことに決めました。
入社前に市販の参考書を購入し、少しずつ学習を始めましたが、知らない言葉や法律ばかりで思うように学習は進みませんでした。
そして入社後の通関士研修で、通関業連合会様のテキストをいただき、講師の方にも直接授業をしていただきました。テキストは法律の条文をもとに、とても細かいところまで説明されており、正直独力では理解しきれない部分が多かったです。しかし講師の方の授業を受けることで、難しい法律の条文の意味を理解でき、絶対に覚えるべき頻出ポイントがわかるようになりました。
学習の流れとしては、講師の方の授業を受けて全体を大まかに把握し、その範囲の問題集をとき、わからないところをテキストや六法で調べ、ノートにまとめるという形でした。特に六法は必ず確認するようにしていました。講師の方の授業で、「実際の試験問題は法律の条文をもとにして出される。早いうちから難しい条文に慣れておく必要がある。」と聞いたためです。土日を中心に学習を進め、平日は通勤時間にまとめたノートを読み返すようにしていました。
1番苦手だったのは通関実務でした。6月時点でまったく手をつけておらず、6月の模試では10点未満しかとることができませんでした。このままでは間に合わないと焦り、そこから過去問題集を中心に実務の学習を始めました。特に輸出入申告問題は配点が大きく、絶対に得点しなければならないと考え、市販のテキストも使いながらひたすら問題を解き続けました。そうするとだんだん傾向やコツが掴めてきて、正答率が上がっていき、8月末の模試では輸出入申告問題できちんと点を取ることができました。直前期は通勤時間に頻出の品目分類を暗記し、休日に過去問を繰り返し解くようにしていました。そして最後の模試では合格点に達することができ、自信を持って試験に臨むことができました。
条文中心の学習と、過去問題集を正解できるまで何度も解くという勉強法が合格のための重要なポイントだったと思います。また何かの目標のため努力し、成果をだすという経験を、社会人になって早いうちにできたのは自信にもつながりました。
最後になりましたが、通関業連合会様のテキストと講師の方々の授業がなければ絶対に合格はできなかったと思います。本当にありがとうございました。またこれから受験される皆様の合格を心よりお祈りしております。